技術情報
鉄系鋳物の鋳造欠陥(ピンホール欠陥・焼付き欠陥)のSEM・EDS分析
| 株式会社ツチヨシ産業 上林仁司・黒川 豊 |
2.SEM・EDSの原理
SEMとは走査電子顕微鏡(Scanning Electron
Microscope)であり,試料に電子線を照射した際に発生する二次電子信号をモニター上で画像化する装置であり,10nm単位
の高倍率・高解像度の画像を得ることができる.
EPMA(Electron Probe X-ray Micro Analyzer)は,試料に電子線を照射した際に発生する特性X線を検出し,含有元素の有無と量を知ることができる装置であり,検出器の違いにより,エネルギー分散型X線分光器(Energy Dispersive X-ray Spectrometer: EDS ,EDX)と波長分散型X線分光器(Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer:WDS,WDX)に分けられる.
それぞれ一長一短がある.
筆者らは,欠陥分析に凹凸 試料の分析が比較的容易なEDSを主に用い,更に詳細な情報を得る際はEPMAを用いている.
Fig.1~3にそれぞれの原理を示す.
EPMA(Electron Probe X-ray Micro Analyzer)は,試料に電子線を照射した際に発生する特性X線を検出し,含有元素の有無と量を知ることができる装置であり,検出器の違いにより,エネルギー分散型X線分光器(Energy Dispersive X-ray Spectrometer: EDS ,EDX)と波長分散型X線分光器(Wavelength Dispersive X-ray Spectrometer:WDS,WDX)に分けられる.
それぞれ一長一短がある.
筆者らは,欠陥分析に凹凸 試料の分析が比較的容易なEDSを主に用い,更に詳細な情報を得る際はEPMAを用いている.
Fig.1~3にそれぞれの原理を示す.
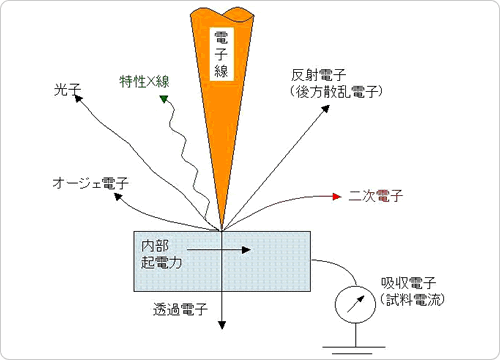
▲Fig.1 電子線照射による電子情報
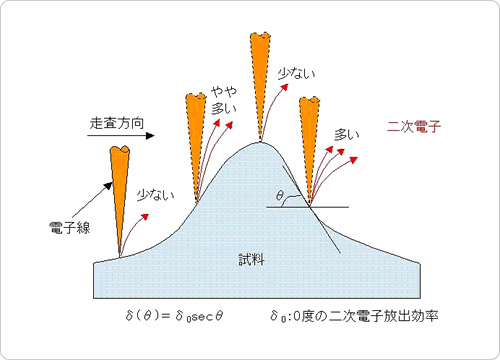
▲Fig.2 SEMの原理(試料の凹凸と二次電子)
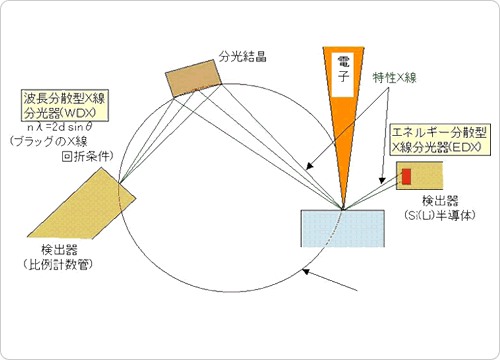
▲Fig.3 EDS,EPMAの原理
|
戻る |
トップへ |
次へ |

