技術情報
生型材料及び生型試験法の基礎(改訂版)
| 株式会社ツチヨシ産業 水田豊昭・黒川 豊 |
2.生型砂構成物の役割
Table2に生型組成物の役割と目的の一覧表を示す.
生型砂の組成で最も量が多いのは前述したようにけい砂であり,これの役割は耐火物として鋳型を保持することである.
次いで主粘結剤であるベントナイトと水,二次粘結材である澱粉と石炭粉,注湯によって生成したオーリチックや不活性微粉等である.
生型砂の組成で最も量が多いのは前述したようにけい砂であり,これの役割は耐火物として鋳型を保持することである.
次いで主粘結剤であるベントナイトと水,二次粘結材である澱粉と石炭粉,注湯によって生成したオーリチックや不活性微粉等である.
| Table2 生型砂組成物の役割と目的 |
| sand | 耐火物(refractory material) | |
| bentonite | 主粘結剤(binder,MB-clay) | |
| moisture | ベントナイト等と水和することで粘結力が発生する | |
| sea coal | 焼付き欠陥対策,ピンホール(FCD)対策,崩壊性改良 | |
| oolitic material | ベントナイト等が焼結し多孔質なガラス状物質としてけい砂に付着する | |
| inert fines |
ベントナイト等が焼結し微粉化した物がメイン. 20μ m以下でMB-clayでない物質 ,揮発成分は含まない |
|
| carbonaceous material |
sea coal starch core binder |
有機質の揮発成分 |
| metallics | 金属ガスが鋳型中で冷却.湯玉 ,バリ等 | |
| loss on ignition | 無機・有機の揮発成分 | |
Fig.2は,石英量の変化と生型組成組成の例である.
石英量は鋳造欠陥と密接な関係がある.その量が少なくても多くても鋳造欠陥が発生する.
Fig.2(A)は石英量が多い例であるが,この時は鋳型が高膨張となり,すくわれ・しぼられ系の欠陥が発生しやすい.
Fig.2(B)は石英量が少ない例であり,この際は耐火度不足のために焼付き欠陥が発生しやすい.
Fig.2(C)は石英量のバランスがとれ,良好な鋳造条件となる.
以下に,それぞれの生型組成物について適正な量・使用方法について詳述する.
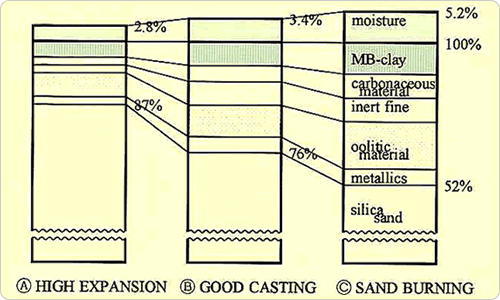
▲Fig.2 生型砂組成のモデル
|
戻る |
トップへ |
次へ |

