技術情報
生型材料及び生型試験法の基礎(改訂版)
| 株式会社ツチヨシ産業 水田豊昭・黒川 豊 |
4.生型砂の管理法
| ■3-管理のための試験方法 |
●コンパクタビリティ(Compactability)
コンパクタビリティは,生型砂が3360μmの篩いを通過させ,φ50×110の容器に投入し,3回ラミングした試験片の高さにより,次式から計算できる.
コンパクタビリティは,生型砂が3360μmの篩いを通過させ,φ50×110の容器に投入し,3回ラミングした試験片の高さにより,次式から計算できる.
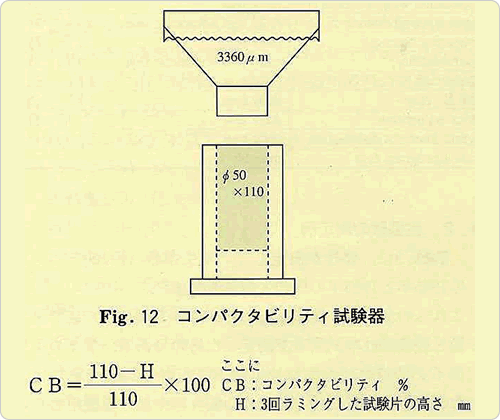
▲Fig.12 コンパクタビリティ試験器
測定方法から明らかなように,コンパクタビリティは,流動性を表す特性である.
また,コンパクタビリティは,およそ25~55%の間で水分と相関があり,Fig.13に見られる様な直線的な関係がある.
したがって,コンパクタビリティを測定することで水分を推定することができる.
ただし,これは活性粘土分,全粘土分,オーリチック分などの生型砂組成が一定の時に当てはまる.
つまり,コンパクタビリティと水分の相関が無くなる時は,生型砂組成が変化している時と判断することができる.
また,コンパクタビリティは,およそ25~55%の間で水分と相関があり,Fig.13に見られる様な直線的な関係がある.
したがって,コンパクタビリティを測定することで水分を推定することができる.
ただし,これは活性粘土分,全粘土分,オーリチック分などの生型砂組成が一定の時に当てはまる.
つまり,コンパクタビリティと水分の相関が無くなる時は,生型砂組成が変化している時と判断することができる.
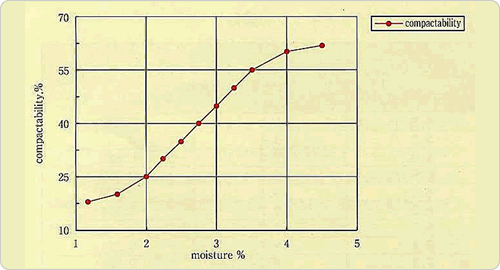
▲Fig.13 コンパクタビリティと水分の関係
コンパクタビリティは,管理値として適正な値を決める必要がある.
最近の高速・高圧造型機では,造型時に35%前後に管理する事が多い.
低圧造型機では40~50%になる.コンパクタビリティは,低い場合と高い場合で発生する問題が異なる.そのために適正な値を決める必要がある.
Table10にコンパクタビリティの変化による問題をまとめた.
●水分(Moisture)
水分は,コンパクタビリティと相関があるために,水分量の変化と鋳造欠陥の関係は,Table6と同一となる.
生型砂組成が一定の時,相関があるために,相関がなくなった時は,生型砂組成が変化したと考えればよい.
コンパクタビリティが一定であるにもかかわらず,水分が増加している場合と減少している場合の生型砂組成の変化をTable11にまとめた.
水分は生型砂の電気抵抗,密度,トルク,電磁波等から間接的に自動測定することが可能ではあるが,データをコンバートする際にエラーが生じやすい.
生型砂を乾燥して測定する方法は正確であるが,測定に時間を要する.自動測定で頻度よく測定し,1日に1度か2度乾燥による方法でチェックするとよい.
●試験片重量(密度)(Specimen weight(density))
試験片密度は,抗圧力を測定する際の試験片の密度である.試験片密度が低いことはオーリチックが増加していることを示している.その結果,焼付き(目さし)が増加し, 生型砂の水分添加量が増加する.試験片密度が高い場合は,膨張系の欠陥や砂かみ欠陥が増加する.
Fig.14に,試験片重量と石英含有量の関係を示した.
試験片重量を測定する事で石英含有量を推定する事が可能である.石英含有量は,シリカプログラム試験で正確な値を測定できる.試験片重量からの推定は,エラーが入りやすいが迅速である.
最近の高速・高圧造型機では,造型時に35%前後に管理する事が多い.
低圧造型機では40~50%になる.コンパクタビリティは,低い場合と高い場合で発生する問題が異なる.そのために適正な値を決める必要がある.
Table10にコンパクタビリティの変化による問題をまとめた.
| Table10 コンパクタビリティの高低による問題 |
| low level | high level |
|
a)sand inclusions b)mold drop c)erosion d)crush e)broken edges f)scab g)expansion defects |
a)oversize castings b)mold-wall movement c)blowholes d)pinholes e)rough surfaces f)shake-out problems g)collapsibility h)penetration i)burn on |
●水分(Moisture)
水分は,コンパクタビリティと相関があるために,水分量の変化と鋳造欠陥の関係は,Table6と同一となる.
生型砂組成が一定の時,相関があるために,相関がなくなった時は,生型砂組成が変化したと考えればよい.
コンパクタビリティが一定であるにもかかわらず,水分が増加している場合と減少している場合の生型砂組成の変化をTable11にまとめた.
| Table11 生型砂組成の変動と水分の関係 |
| increasing moisture | decreasing moisture |
|
a)increase in MB-clay b)increase in total clay c)increase in oolitics d)increase in fines e)increase in additives f)low mixing efficiency |
a)reduction in MB-clay b)reduction in total clay c)reduction in oolitics d)reduction in fines e)reduction in additives f)high mixing effeciecy |
水分は生型砂の電気抵抗,密度,トルク,電磁波等から間接的に自動測定することが可能ではあるが,データをコンバートする際にエラーが生じやすい.
生型砂を乾燥して測定する方法は正確であるが,測定に時間を要する.自動測定で頻度よく測定し,1日に1度か2度乾燥による方法でチェックするとよい.
●試験片重量(密度)(Specimen weight(density))
試験片密度は,抗圧力を測定する際の試験片の密度である.試験片密度が低いことはオーリチックが増加していることを示している.その結果,焼付き(目さし)が増加し, 生型砂の水分添加量が増加する.試験片密度が高い場合は,膨張系の欠陥や砂かみ欠陥が増加する.
Fig.14に,試験片重量と石英含有量の関係を示した.
試験片重量を測定する事で石英含有量を推定する事が可能である.石英含有量は,シリカプログラム試験で正確な値を測定できる.試験片重量からの推定は,エラーが入りやすいが迅速である.
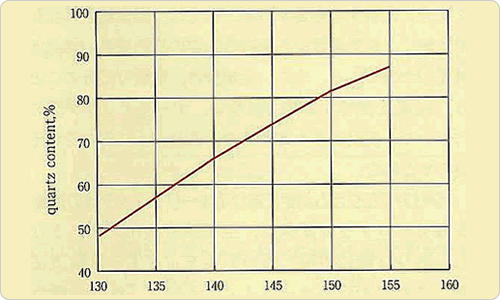
▲Specimen weight,g
Fig.14 試験片重量と石英量の関係
●抗圧力,せん断力(Green compression strength, Shearing
strength)
湿態抗圧力は,生型砂の強度を代表的に表す特性である.
ベントナイト添加量が15%までは,量が増えるにしたがって抗圧力が増加する.15%以上になるとけい砂の内部摩擦応力が低下するために,抗圧力がサチレイトしそれ以上は上がらなくなる.
鋳物砂の強度発現は以下の要因から成り立っている.
(1)クーロン力(Coulomb's force)
(2)ファン・デル・ワールス力(Van der Waals' force)
(3)水の表面張力(surface tension of water)
(4)けい砂の内部摩擦応力(frictional stress of sand grain)
鋳物砂は,けい砂-ベントナイト-水の混合物であり,それらの比率は一般的には,けい砂は85~95%,ベントナイトは3~15%,水は1~7%である.これらの比率の中で,ベントナイトに対して水が20~35%の間で最も抗圧力が高くなる.また,混練効率が強度に対して重要なファクターとなる.
抗圧力の他に,鋳型の強度を測定する方法としては,せん断力,引張力ある.これらは,強度発現の要因の内,内部摩擦応力の寄与率が小さくなり,(1)~(3)のベントナイト-水の要因が高くなる.
抗圧力は(4)の寄与率が高い.抗圧力を測定すると,砂-ベントナイト-水の強度が測定でき,剪断力や引張力を測定すると,ベントナイト-水の強度を測定することになる.
●通気度(Permeability)
通気度は,試験片密度に左右される特性であり,試験片密度が上昇するにしたがって低下する.
試験片密度と通気度の間には,高い負の相関がある.
ただし,試験片密度が各生型砂組成の比重と生型砂特性の充填性の影響を受けるのに対して,湿態通気度は,生型砂 特性の充填性と鋳物砂の粒度構成の影響を受ける.
通気度の値は,一般的には120~180が主体である.通気度が低いと,ガス欠陥(ブローホール)が発生しやすくなるが,鋳肌は良好になる.
逆に通気度が高くなるとガス欠陥は少なくなるが,物理的焼付き欠陥が発生しやすくなる.
また,鋳型の熱伝導性は,空気(蒸気)を媒体として熱が伝わるので,通気度が高いと熱が伝わりやすくなる.
●全粘土分(Total clay)
全粘土分は,JIS Z 2601(鋳物砂の粘土分試験方法)によって測定できる.
この粘土分は粘土鉱物学的な粘土を指すものではなく,20μm以下の粒子を意味する.
つまり,20μm 以下の粒子であれば,ベントナイト,けい砂,澱粉,石炭粉等の微粒子を全て指す.測定はストークスの法則を利用している.
20μm以上の粒子は,水中では5分間で150mm以上沈降しない性質を利用して測定している.
●活性粘土分(Active clay,M.B.clay)
活性粘土分は,鋳物砂中のベントナイト量を直接的に求める方法である.
ベントナイトがメチレンブルー(methylen blue)を吸着することを利用した試験である.
ベントナイトは種類によって,methylen blueを吸着する量が異なり,鋳物砂のメチレンブルー吸着量を測定するとベントナイトの吸着量から計算できる.
活性粘土分を測定する際に,鋳物砂の分散方法を変えると測定値が異なってくる.
これは,ベントナイトが熱影響により結晶相関が接近しかけているからである.
強力に分散させると接近しかけたベントナイトも定量することができる.分散方法が弱いと層間の離れたベントナイトのみの定量となる.強力な分散方法とは,ピロリン酸ソーダを分散剤にして煮沸撹拌する方法である.弱い分散方法とは,硫酸を分散剤にして超音波で分散させる方法である.
●灼熱減量(Loss on ignition)
灼熱減量は,乾燥鋳物砂を1000℃で2時間焼成した時の減量パーセントである.
意味するところは,石炭粉,澱粉等の二次添加材,ベントナイト,けい砂の結晶水,中子等に含まれるバインダーなどである.
二次添加材を使用しない鋳物工場では,灼熱減量が1%前後になる.鋳物工場全体の平均は3%程度になる.
鋳物工場の砂管理者の考えによって異なるが,FCDのラインでは石炭粉を多く添加し灼熱減量を4%程度に管理するケースがある.石炭粉から発生する還元性ガスによって,ピンホールが抑制されるからである.
FCのラインでは,通常は2.5~3.0% である.灼熱減量が少ないと物理的焼付き(目さし)が発生し,多いとブローホールが発生する.
FCとFCDを交互に鋳込むラインでは,灼熱減量の設定に苦慮する.FCDにおけるピンホールの発生具合で設定値を決めている.
●粒度分布(Grain fineness distribution)
粒度分布は解粒法と団粒法がある.
解粒法は,粘土分を除去した後の鋳物砂の粒度分布である.
団粒法は,粘土分を除去しないで乾燥のみ鋳物砂に加えた後に粒度分布を測定したものである.
2つの粒度分布を対比すると粘土分の付着具合が判断できる.例えば,200mesh以降で解粒法と団粒法に差があれば,微粉状態の粘土が多いと考えられる.
また,26mesh以上でそれらの差が多いと,ダマが多いと考えられる.
湿態抗圧力は,生型砂の強度を代表的に表す特性である.
ベントナイト添加量が15%までは,量が増えるにしたがって抗圧力が増加する.15%以上になるとけい砂の内部摩擦応力が低下するために,抗圧力がサチレイトしそれ以上は上がらなくなる.
鋳物砂の強度発現は以下の要因から成り立っている.
(1)クーロン力(Coulomb's force)
(2)ファン・デル・ワールス力(Van der Waals' force)
(3)水の表面張力(surface tension of water)
(4)けい砂の内部摩擦応力(frictional stress of sand grain)
鋳物砂は,けい砂-ベントナイト-水の混合物であり,それらの比率は一般的には,けい砂は85~95%,ベントナイトは3~15%,水は1~7%である.これらの比率の中で,ベントナイトに対して水が20~35%の間で最も抗圧力が高くなる.また,混練効率が強度に対して重要なファクターとなる.
抗圧力の他に,鋳型の強度を測定する方法としては,せん断力,引張力ある.これらは,強度発現の要因の内,内部摩擦応力の寄与率が小さくなり,(1)~(3)のベントナイト-水の要因が高くなる.
抗圧力は(4)の寄与率が高い.抗圧力を測定すると,砂-ベントナイト-水の強度が測定でき,剪断力や引張力を測定すると,ベントナイト-水の強度を測定することになる.
●通気度(Permeability)
通気度は,試験片密度に左右される特性であり,試験片密度が上昇するにしたがって低下する.
試験片密度と通気度の間には,高い負の相関がある.
ただし,試験片密度が各生型砂組成の比重と生型砂特性の充填性の影響を受けるのに対して,湿態通気度は,生型砂 特性の充填性と鋳物砂の粒度構成の影響を受ける.
通気度の値は,一般的には120~180が主体である.通気度が低いと,ガス欠陥(ブローホール)が発生しやすくなるが,鋳肌は良好になる.
逆に通気度が高くなるとガス欠陥は少なくなるが,物理的焼付き欠陥が発生しやすくなる.
また,鋳型の熱伝導性は,空気(蒸気)を媒体として熱が伝わるので,通気度が高いと熱が伝わりやすくなる.
●全粘土分(Total clay)
全粘土分は,JIS Z 2601(鋳物砂の粘土分試験方法)によって測定できる.
この粘土分は粘土鉱物学的な粘土を指すものではなく,20μm以下の粒子を意味する.
つまり,20μm 以下の粒子であれば,ベントナイト,けい砂,澱粉,石炭粉等の微粒子を全て指す.測定はストークスの法則を利用している.
20μm以上の粒子は,水中では5分間で150mm以上沈降しない性質を利用して測定している.
●活性粘土分(Active clay,M.B.clay)
活性粘土分は,鋳物砂中のベントナイト量を直接的に求める方法である.
ベントナイトがメチレンブルー(methylen blue)を吸着することを利用した試験である.
ベントナイトは種類によって,methylen blueを吸着する量が異なり,鋳物砂のメチレンブルー吸着量を測定するとベントナイトの吸着量から計算できる.
活性粘土分を測定する際に,鋳物砂の分散方法を変えると測定値が異なってくる.
これは,ベントナイトが熱影響により結晶相関が接近しかけているからである.
強力に分散させると接近しかけたベントナイトも定量することができる.分散方法が弱いと層間の離れたベントナイトのみの定量となる.強力な分散方法とは,ピロリン酸ソーダを分散剤にして煮沸撹拌する方法である.弱い分散方法とは,硫酸を分散剤にして超音波で分散させる方法である.
●灼熱減量(Loss on ignition)
灼熱減量は,乾燥鋳物砂を1000℃で2時間焼成した時の減量パーセントである.
意味するところは,石炭粉,澱粉等の二次添加材,ベントナイト,けい砂の結晶水,中子等に含まれるバインダーなどである.
二次添加材を使用しない鋳物工場では,灼熱減量が1%前後になる.鋳物工場全体の平均は3%程度になる.
鋳物工場の砂管理者の考えによって異なるが,FCDのラインでは石炭粉を多く添加し灼熱減量を4%程度に管理するケースがある.石炭粉から発生する還元性ガスによって,ピンホールが抑制されるからである.
FCのラインでは,通常は2.5~3.0% である.灼熱減量が少ないと物理的焼付き(目さし)が発生し,多いとブローホールが発生する.
FCとFCDを交互に鋳込むラインでは,灼熱減量の設定に苦慮する.FCDにおけるピンホールの発生具合で設定値を決めている.
●粒度分布(Grain fineness distribution)
粒度分布は解粒法と団粒法がある.
解粒法は,粘土分を除去した後の鋳物砂の粒度分布である.
団粒法は,粘土分を除去しないで乾燥のみ鋳物砂に加えた後に粒度分布を測定したものである.
2つの粒度分布を対比すると粘土分の付着具合が判断できる.例えば,200mesh以降で解粒法と団粒法に差があれば,微粉状態の粘土が多いと考えられる.
また,26mesh以上でそれらの差が多いと,ダマが多いと考えられる.
|
戻る |
トップへ |
次へ |

